「介護はいつか誰もが受けることになる」
これは避けられない現実です。
しかし、その時期をできるだけ遅らせることはできます。
介護を遅らせることができれば、
- 自分の好きなことに取り組める期間が長くなる
- 入浴や排泄など「他者に助けてもらう」時期を先延ばしできる
- 介護にかかるお金を減らせる
こうした意味でも、「マインドの持ち方」はとても重要です。介護を遠ざけるために役立つ5つのマインドをご紹介します。
① レジリエンス(心理的回復力・立ち直る力)
研究背景
病気や生活の変化に直面したとき、うまく切り替えて前に進む力が「要介護」への移行を遅らせるとされています。
具体例
- 転んで骨折してしまった → 「もう動けない」と諦めず、「リハビリで少しでも歩けるようになろう」と挑戦する。
- 配偶者を亡くした → 孤独で落ち込む一方、「地域のサークルに出てみよう」と新しい繋がりを探す。
② ポジティブ思考(前向きな受け止め方)
研究背景
日常の出来事をポジティブに解釈する人ほど、生活満足度や健康寿命が長いと報告されています。
具体例
- 雨の日に散歩に行けなかった → 「運動できない」と落ち込まず、「部屋でラジオ体操をしよう」と切り替える。
- 孫と遊んで疲れた → 「もう年だから」ではなく、「体力をつけるために筋トレをしよう」と行動につなげる。
③ 成長マインドセット(まだ成長できると信じる姿勢)
研究背景
「人は年齢に関わらず成長できる」と考える人は、活動性を保ちやすいことが示されています。
具体例
- スマホの操作が分からない → 「自分は機械に弱いから無理」ではなく、「少しずつ覚えればできるようになる」と挑戦。
- 新しい料理や体操を教わる → 「もう歳だから覚えられない」ではなく、「工夫すれば楽しめる」と続ける。
④ 主体性・自己効力感(自分で選び、コントロールする感覚)
研究背景
「自分の生活は自分で決められる」という感覚を持つ人は、要介護になるリスクが低いといわれています。
具体例
- デイサービス → 「今日はカラオケより工作をしたい」と自分で選ぶ。
- 食事 → 「出されたものを食べるだけ」ではなく、「減塩にしたいから漬物は控える」と工夫する。
⑤ 意味感・人生の目的(Sense of Purpose)
研究背景
「人生の目的や役割を持つこと」は認知症予防や生活意欲に直結するとされます。
具体例
- 「朝は庭の花に水やりをする」ことで役割を持つ。
- 孫の成長を見たい → 「その日のために元気でいよう」と生活を整える。
まとめ:元気な高齢者の共通点
超高齢になっても元気な方々には共通点があります。
「誰かの世話になりたくない」と口にしなくても、自然とそれが見えるような行動をしています。そうしたマインドと行動の積み重ねが、介護を遠ざける大きな力になります。
「介護を受けないようにする」ことは難しいかもしれません。ですが、「介護を遅らせる」ことは誰にでもできる挑戦です。

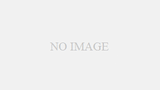
コメント